1 財産分与対象資産の調査
会社経営者の場合、一般の方と違って大きな資産を形成されている方が多いです。
そのため、財産分与の対象となる財産を全て調査して、財産を正確に把握することが必要となります。
会社経営者は、多大な資産を相手方に渡すまいとし財産を隠す傾向がありますから、
離婚を切り出す前に財産調査を終わらせておく必要があります。
何が財産分与の対象になり、それを立証する証拠をどうやって収集するかについては高度な専門的知識・経験が必要です。
したがって、離婚問題を専門とし、財産分与問題について多数の相談・事件を取り扱っている弁護士に相談する必要があります。
2 財産分与対象動産には以下のものがあります。
-
① 不動産(自宅・収益物件)- ② 預貯金
- ③ 保険(生命保険・学資保険等で貯蓄型のもの)
- ④ 動産(車・家財道具等)
- ⑤ 有価証券(株式・会員権等)
- ⑥ 退職金(将来受け取るものも含む)
このうち①不動産②預貯金③保険については、サラリーマン・公務員・大学職員に特有な問題として解説し、
ここでは④動産⑤有価証券⑥退職金について解説します。
〇動産
- 家財道具は一般に時価評価額が極めて低いので、財産的価値を検討して財産分与することはほとんどありません。
テレビ・レコーダー・パソコンなどをどちらが引き取るかが問題になる程度です。 - しかし、会社経営者の場合、夫婦の一方が宝石等の貴金属、高級な時計・自動車、小型船舶などを所持していることがあります。
これらは全て夫婦共有財産になり得ますから、これらを調査・時価評価して財産分与しなければなりません。 - 〇有価証券(株式・会員権等)
- 会社経営者の場合、余った資産で株式投資を行っていることがあります。
このような場合には、その株式を調査・特定して評価し、財産分与の対象とする必要があります。 また、会社が株式会社の場合は、会社経営者は会社の株式を保有していることがほとんどです。
この株式は財産分与の対象となります。
会社経営者が一人で全株式を保有している場合には、会社経営者が株式会社の全資産の所有者となりますから、
株式価格=「株式会社の全資産」となり、株式購入時の株式価格とは比較にならない資産価値を有することになります。
- ただ、この株式の時価評価については高度な専門知識が必要です。
全株式の何割を保有しているかによってその評価額が全く違ってきます。
株式売買価格決定申立などの事件を取扱ったことがあり、株式の評価に精通した弁護士に相談しないと、
その資産価値を見誤ることになりますので、注意が必要です。 - 〇退職金
- 会社経営者は取締役(役員)であって従業員ではないことから、退職金はないと考えておられる方が多いです。
しかし役員であっても、退職金を財産分与の対象とすることができる場合があります。
役員が退職するときに高額な退職金を支給するため、会社が契約者となって保険をかけていることがあるのです。
また、役員退職金規定を定めている会社もあります。
役員だからといって退職金をあきらめてはいけません。
3 財産分与の割合
一般の会社員の場合、夫婦共有財産を財産分与するときには、夫婦それぞれが2分の1ずつ取得します。
たとえ妻が主婦で収入がなかったとしても、妻が育児・家事をしたことは、夫と同じ収入の労働をしたと評価されるのです。
しかし、会社経営者の場合は、それと異なる割合で財産分与が行われることがあります。
夫が会社を経営し、自らの特別な才能・手腕・専門知識により、多額の資産を形成した場合です。
この場合、妻の家事労働による貢献によって形成された資産よりも、夫の才能・手腕・専門知識によって形成された資産の方が多いと考えられるのです。
このような場合、裁判例においても夫7:妻3、あるいは夫6:妻4といった割合で財産分与が行われたものがあります。
いかなる場合に5:5になり、いかなる場合に7:3になるのかは個別具体的な事案を分析しなければなりませんので、
離婚を専門的に行っている弁護士に相談すべきです。
4 婚姻費用・養育費の算定(私立学校の学費問題等)
- ① 算定の困難性
- 婚姻費用・養育費の算定は、夫婦双方の収入に応じて行われます。
家庭裁判所では、夫婦双方の年収から算出される算定表というものを作成しており、多くの場合は、これに基づいて算定されます。
ところが、この算定表は一般的な世帯を対象としているため、年収2000万円以上については記載がありません。
年収2000万円以上の会社経営者の場合は、個別具体的な事案を加味して複雑な計算式によって算出されます。
したがって、妥当な婚姻費用・養育費を算定するには、離婚問題についての高度な専門知識が必要となります。 - ② 他の収入の考慮
- 会社経営者は多くの資産を形成していることから、他に収入があることがあります。
例えば、不動産を賃貸した場合の収入・株式の配当・他の会社を経営したことによる収入、
他の会社の従業員としての給与収入などです。
婚姻費用・養育費の算定はこれらも調査して加えたうえで行わなければなりません。 - ③ 私立学校の学費
- 会社経営者は子どもを私立学校に通わせていることが多いです。
ところが、算定表は公立学校の学費を基にして作成されています。
したがって、子どもを私立学校に通わせている場合は、算定表で算出される金額に上乗せして、
私立学校学費分を別途婚姻費用・養育費として請求できる場合があります。
離婚を専門にやっていない弁護士にはこれを知らない弁護士が多く、そのような弁護士が相手方に就くと解決が遅れます。会社経営者が私立学校進学を承諾していたかどうか、会社経営者の収入はどの程度かによって請求できるかどうかが変わりますし、請求できる場合でも、私立学校学費の何割を請求できるかは、事案によって異なります。
離婚について専門知識のない弁護士に相談されると誤った解決がなされる可能性がありますので注意が必要です。
5 解決事例
経営者が依頼者、または相手方が経営者の解決事例はこちら>>

 寺尾 浩(てらお ひろし)
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
過去の解決実績はこちらから
【アクセスマップ】
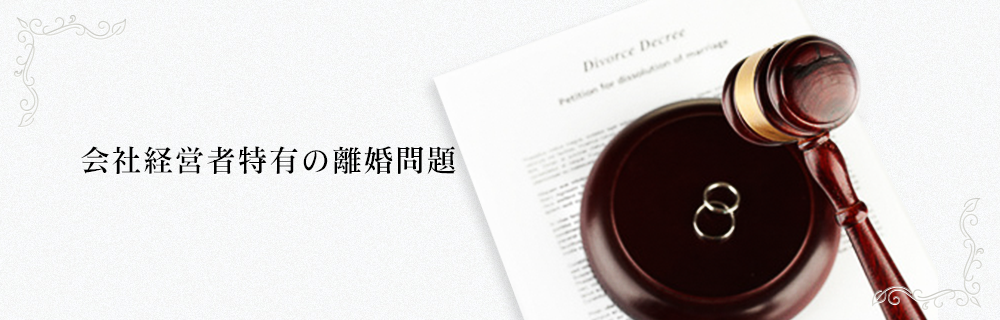
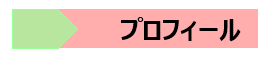
 寺尾 浩(てらお ひろし)
寺尾 浩(てらお ひろし)