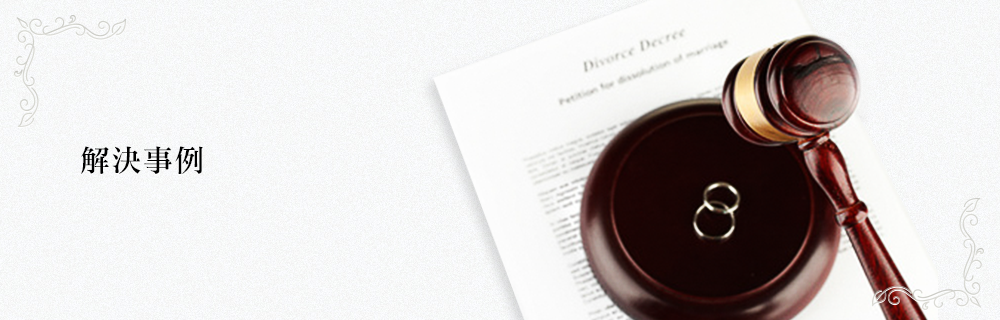
夫の依頼した弁護士の対応が遅いため、調停を申し立てて離婚を成立させた事例
依頼者 妻
夫 26歳 会社員 大阪府大阪市在住
妻 26歳 看護師 大阪府箕面市在住
離婚原因 精神的虐待、性格の不一致
きっかけ 夫の依頼した弁護士と連絡が取れなくなった
財産 預貯金
子ども なし
Aさんは、夫Bからの精神的虐待等に耐えられなくなって夫Bと別居し、夫Bに対して離婚を求めました。
その後、夫Bは弁護士Cに依頼しましたが、その後、突然Cからの連絡が途絶え、AさんがCにメールで連絡しても、全く返信がない状態が続きました。
そのため、Aさんは夫Bとの離婚協議を当方に依頼されました。
弁護士はCの所属する法律事務所に連絡し、Cと夫Bとの委任契約が現在も継続しているのか至急回答するように求めました。
それでも同法律事務所からはなかなか回答がなかったため、弁護士は離婚調停を申し立てました。
すると、ようやく上記法律事務所の別の弁護士から「Cは体調不良で対応できなくなったので、同じ事務所の別の弁護士が今後対応する。」と連絡がありました。
その後の調停手続きでは、夫Bも離婚について争わず、財産分与のみが争点となったため、主として財産分与の協議を行うことになりました。
ただ、Aさんは早期離婚を希望していましたが、夫Bの開示準備が遅かったため、なかなか財産分与の協議を開始できませんでした。
そこで、弁護士は期日間に督促したり、調停委員から夫Bの財産資料の提出期限を明確に定めてもらう等して、できるだけ早く財産分与の協議を行うことができるように働きかけ、夫Bの財産資料を開示させました。
その後の調停での協議の結果、Aさんと夫Bの婚姻期間はかなり短く、子どももいなかった点を考慮し、双方の婚姻時の預貯金が別居時点でも残存していると仮定して、別居時点の双方の財産からそれぞれの婚姻時の預貯金残高を差し引く形で共有財産の範囲を確定することになりました。
その上で、Aさん名義の共有財産の方が夫B名義の共有財産よりも多かった(Aさんと夫Bの年収はほぼ同じであり、かつ、主として夫Bの給与を生活費に充てていた)ので、最終的にAさんから夫Bに財産分与として約97万円を支払う内容で離婚調停を成立させました。
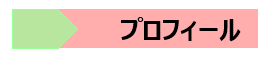
 寺尾 浩(てらお ひろし)
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
【アクセスマップ】