退職金の財産分与
目次
財産分与の対象は、預貯金や給与・不動産・住宅ローン・保険金など、多岐に渡りますが、退職金も含まれます。
既に支払われた退職金は、当然、財産分与の対象となり、争いになることはほとんどありません。
まだ支払われていない退職金の場合どうなるかについて離婚を専門としない弁護士の中にはご存知ない方が多いです。
現在では、大阪家庭裁判所でも東京家庭裁判所でも、「まだ支払われていない退職金も財産分与の対象とする。」という運用がなされています。
かつて裁判所は、「退職まで7年以内であれば、財産分与の対象とする」という運用をしていました。そのため60歳定年の場合、53歳を超えるかどうかが一つの基準となっていました。会社は倒産する可能性がありますので、あまりにも将来の退職金については、財産分与の対象外とされていたのです。
法律専門書にも同様なことが書かれています。そのため弁護士の中にも、かつての裁判所の運用を説明する人がいるのです。
退職金は労働の後払的性格のものですから、現在では、いかに若くとも退職金は財産分与の対象とされます。
具体的には、別居時に自己都合退職した場合の退職金を算出し、それを財産分与対象財産とするのです。
この裁判所の運用に即した戦略が必要になってきます。
退職金については最新の裁判所の動向に即した戦略が必要となります。離婚問題について研鑽を積んでいる経験豊富な弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
⑴ 退職金は離婚時に、 財産分与の対象となる のが一般的です。
会社の退職金規程などに基づいて支給される退職金は、賃金の後払的性質を有すると考えられています。そのため退職金は、婚姻期間中に夫婦が協力して形成・維持してきた財産であると評価でき、財産分与の対象となります。
退職金は将来支払われるものですから、かつては、支払われるかどうかの確実な場合(数年内に定年退職する場合)にのみ認められていましたが、現在では、原則として財産分与の対象財産とされます。
⑵ 同居期間に対応する退職金の2分の1が分与されるのが基本
① 定年時に支払われる退職金の2分の1が分与されるのか?
退職金を財産分与する場合、定年時に支払われる退職金の2分の1が分与されるのではありません。 別居時に自己都合退職した場合に支給される退職金 が財産分与算定の基礎となります。
② 別居時に自己都合退職した場合に支給される退職金の2分の1が分与されるのか?
他の共有財産と同様に、退職金も基本は2分の1が配偶者に分与されます。ただし、財産分与の対象となる退職金の額は、別居時に自己都合退職した場合に支給される退職金全額の2分の1ではありません。
別居時に自己都合退職した場合に支給される退職金のうち 同居期間に対応する額の2分の1に限定されます 。
別居時に自己都合退職した場合に支給される退職金は、就職時から別居時までに対応した退職金です。独身時代(婚姻前)に勤務した部分も含まれていることがあります。しかし、財産分与の対象となるのは、結婚後別居するまでの期間(同居期間)に対応する部分だけです。婚姻前に勤務していた期間や、別居してから離婚するまでの間に勤務していた期間に対応する部分の退職金は、財産分与の対象にはなりません。
例えば、別居時までに夫が30年勤務していて、結婚から別居時まで20年経過していた場合、別居時に自己都合退職した場合に支給される退職金(仮に300万円とします)のうち30分の20(3分の2)だけが財産分与の対象となり、その2分の1を財産分与されます。したがって、別居時に自己都合退職した場合に支給される退職金の3分の1(前述の例だと100万円)が分与されることになります。
なお、退職金を既に受け取っていた場合は、財産分与の基準時(別居時)に現存する場合に限り分与の対象となります。
また、財産分与の割合については、基本は2分の1と考えられていますが、当事者間の合意によってこの割合を変更することも可能です。
⑶ 定年前(退職金を受け取る前)でも対象となる
別居時に自己都合退職した場合に支給される退職金を会社が算出してくれたとしても、実際に退職しない限り退職金は支給されません。そのため、「まだ退職金は支給されていないので、支払えない。」と反論する人がいます。しかし、このような反論は裁判では認められません。
定年前(退職金を受け取る前)であっても、離婚時に財産分与する必要があります。
では、どのように計算するのでしょうか。離婚時に退職金がすでに支払われている場合と、退職前でまだ支払われていない場合について、それぞれ計算事例とともに紹介します。
⑴金が既に支払われている場合、退職金は預貯金口座に送金されています。その後、自動車や株式などの動産を購入したり、遊興費に費消したりして形を変えることになります。これらのうち、別居時に残存したものが財産分与対象財産となります。
別居時に預貯金として残っている場合はその預貯金が財産分与対象財産となり、自動車や株式として別居時に残っている場合はその自動車や株式が財産分与対象財産となります。
⑵ 退職前で、まだ退職金をもらっていない場合
退職前で退職金をもらっていない場合の退職金については、別居時に自己都合退職した場合に支給される退職金を元にして計算されます。
実際には退職していないのですから、別居時に自己都合退職した場合に支給される退職金がいくらなのか、会社に算出してもらい、証明書を発行してもらう必要があります。
【具体的算出例】
別居時に自己都合退職した場合に支給される退職金が200万円で、勤続年数が20年、婚姻から別居までの期間が10年とすると、退職金の分与額は50万円となります。
200万円×婚姻期間10年÷勤続年数20年×0.5=50万円
退職金の財産分与は、離婚時に支払うことが原則となります。しかし、 定年前の場合は離婚時にまだ退職金が支給されていないため、財産分与する側に資力がない ことも考えられます。このような場合、どのようにして財産分与を行うのでしょうか?
⑴ 他の財産で支払う
まず考えられるのは、他の財産で支払う方法です。財産分与する時点において退職金分の現金がなかったとしても、その他の資産で調整を図ることが考えられます。
例えば、 自宅不動産・株式等の金融資産がある場合は、その自宅や金融資産を財産分与するなどの方法で退職金分を支払う ことができます。また、離婚時に自宅を売却し、その売却代金から支払うこともあります。
⑵ 分割払いにする
一度に大きな額を支払えない場合は、分割払を提案することも可能です。ただし、 相手方には分割に応じる法的義務はありませんから、分割払にできるかどうかは相手方との交渉次第となります。したがって、必ず分割払に応じてもらえるわけではありません から注意が必要です。
相手方と合意できない場合は、基本的に財産分与金を一括で支払う必要があり、支払えない場合は、財産に強制執行されるリスクがあります。
なお、退金を財産分与される側の場合は、分割払金の支払が滞った場合のペナルティを条項化することが必要です。
⑶ 退職金の受け取り後に分与する
退職金を財産分与する側に離婚時に十分な資力がない場合や、退職金の支給時期が相当先である場合には、退職金の受け取り後に分与する方法がとられることもあります。
ただしこれも、退職金を分与される側の承諾が必要です。
この方法は、退職時期が不明なため、退職金を分与される側からすれば、知らない間に退職されて退職金を費消されたりするなどして、結果的に回収できない可能性があります。
⑴ 離婚協議や調停で条件を提示する
まずは、別居時に自己都合退職した場合に支給される退職金がいくらなのか、会社に算出してもらい、証明書を発行してもらうよう相手方を説得することになります。
次に、退職金を含む全財産を開示させ、財産目録を作成します。その財産目録を元に離婚条件について合意を形成します。相手方と離婚条件について合意ができたら、 後のトラブルを防ぐため、弁護士を入れて合意内容を文書化(内容によっては公正証書化)する ことが必要です。
この場合、合意に至った金額を確実に受け取る方策を取っておく必要もあります。
交渉では相手方と離婚条件について合意できそうにないときは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停では、調停委員という第三者を介して、相手と顔を合わせることなく話し合いを進めることができます。ただ、調停委員は法律の専門家ではありませんから、法的に誤ったアドバイスをしたり、聞く耳を持たない当事者を説得することをあきらめ、誠実な当事者にばかり譲歩を求める方もおられます。
したがって、退職金などの財産が多い方が調停に移行した場合には、最初から弁護士を入れたほうがいいでしょう。
調停が成立すれば、合意の内容は「調停調書」として残ります。ただ、約束を守ってもらえなかった場合のペナルティを条項化しておかないと、強制執行の手続きをとることができなくなったり、すぐに強制試行できなくなるので注意が必要です。
⑵ 合意を得られなければ裁判する
離婚調停を行っても離婚条件の合意が得られないときは、離婚裁判を提起して裁判所に判断を委ねます。当事者の合意を重視する調停とは違い、離婚条件についての最終的な判断を裁判官は行わなければならないため、 裁判官を納得させるだけの証拠を提出しなければならず、それが提出できない場合は敗訴する(こちらの要求は認められない)ことになります 。
また、独特な法律用語に従って書面を提出する必要があります。
一般の方がこのような活動を行うことは難しいです。ご本人だけで訴訟活動を行おうとしても、裁判所から弁護士に依頼するよう説得されることが多いです。
⑶ 離婚後でも請求はできる
離婚後であっても財産分与を請求することは可能です。
離婚と同様にまずは交渉から始めることになります。
ただ、交渉によって決めることができない場合は、 離婚が成立した日から2年以内に家庭裁判所に調停または審判の申立てをする必要があります 。
「退職金が財産分与の対象になるのか?」「財産分与によって受け取れる退職金は具体的にはいくらなのか?」「相手方にどのような書類を提出させるべきなのか?」など、退職金について疑問・悩みがあるときは、まずは弁護士に相談しましょう。退職金の問題は、その計算方法や支払確保の方法など、一般の方では対処できない問題が多く、ご自身で判断することが難しいケースが多いといえます。弁護士であれば、 退職金として請求できる財産分与額を含めた全財産分与について、法律上適正な請求をすることができます 。
ただし、離婚に精通した弁護士に相談する必要があります。
離婚事件の取扱件数が少ない弁護士の中には、退職金が財産分与の対象になることを知らない方や、「退職まで数年に迫っている場合しか退職金は財産分与の対象にならない」といったような古い考え方(かつての専門書に記載されていた)に基づいてアドバイスされる方がおられるからです。
離婚に際しては決めなければならないことが多く、一つ一つについて正確な判断を下すのは難しいものですが、中でもお金の問題は正確な知識が必要です。一つ一つの財産について、それが財産分与の対象になるのか、なるとしてどのように計算するのか、一般の方にはなかなかわかりにくいため、財産分与が多い方の離婚交渉は当事者のみでは困難なことがあります。
弁護士に依頼すると、退職金だけでなく全ての財産分与の問題についてアドバイスがもらえますし、財産分与以外の離婚条件なども含めて相手方との交渉 を行ってくれます。また、交渉が難航して調停・裁判に進んだとしても、強気で押していくべき場面なのか、強気で押し続けるとかえって利益を損ねる場面なのかを、その時々に応じてサポートしてもらえます。最終的に合意ができる場合も、どのような文言で合意すべきか、不払いが生じないように合意内容を確実に履行させる方策を講じることができます。これらの点が弁護士に依頼するメリットだといえるでしょう。
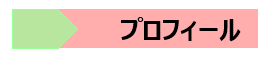
 寺尾 浩(てらお ひろし)
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
【アクセスマップ】